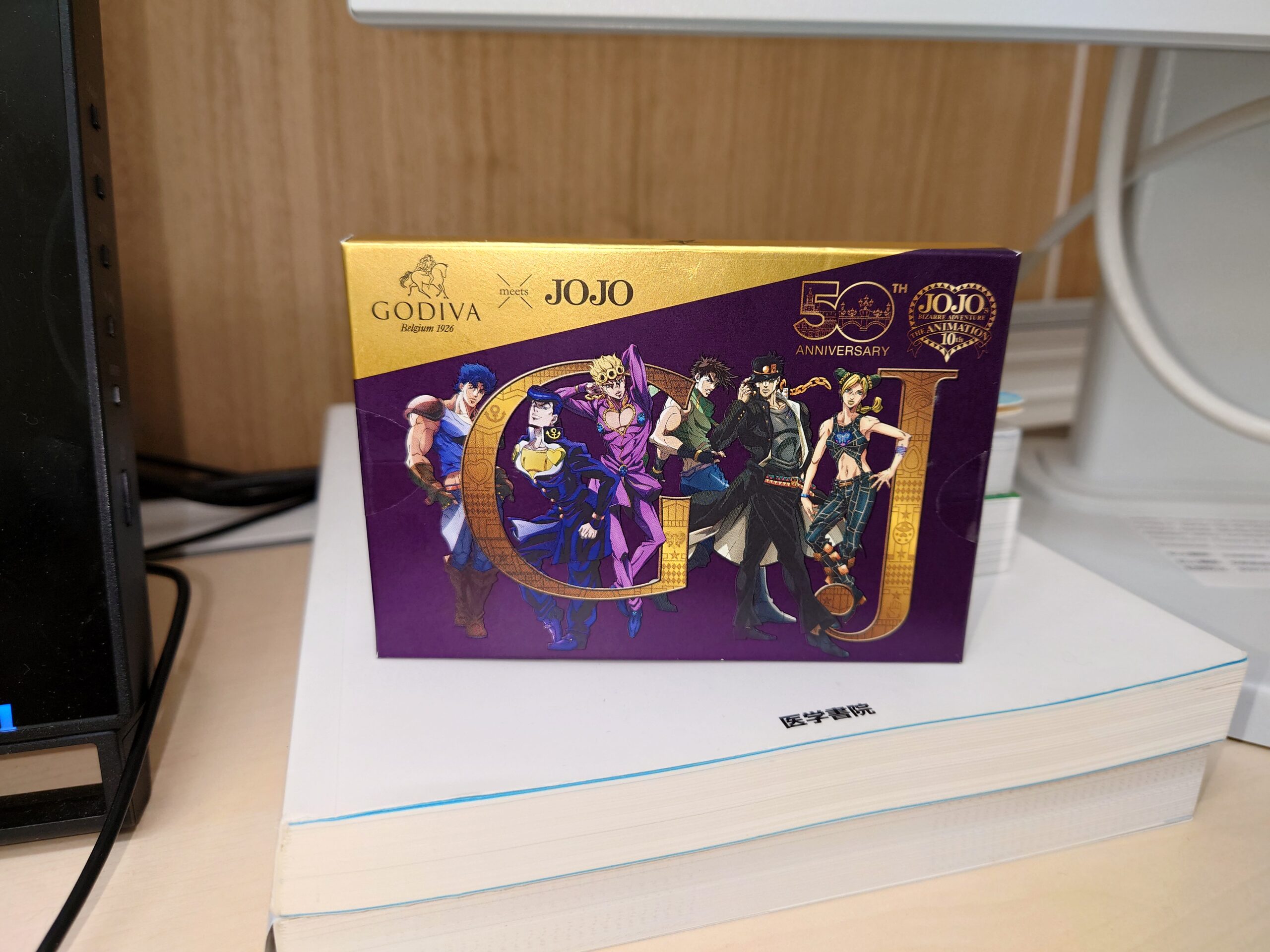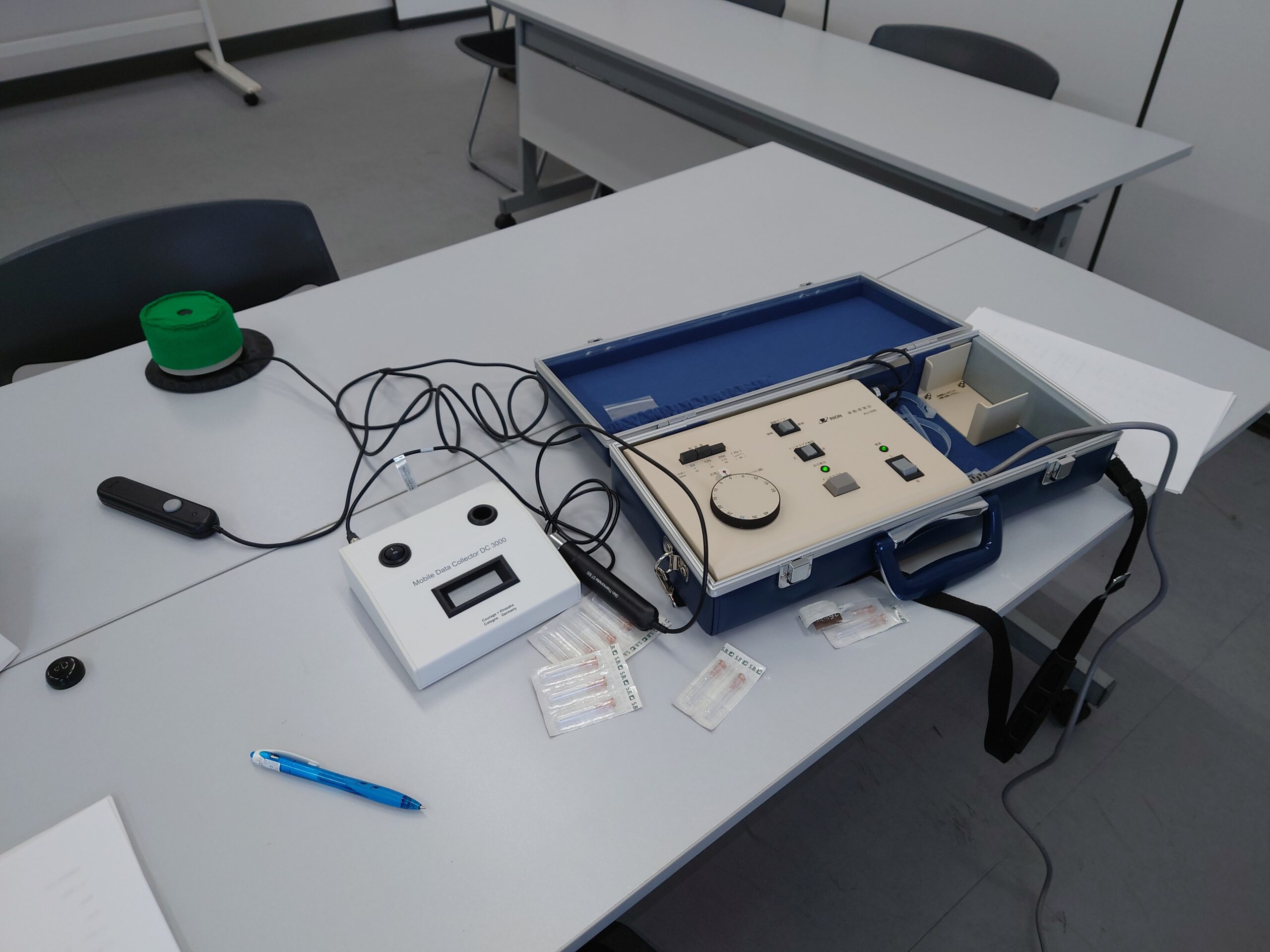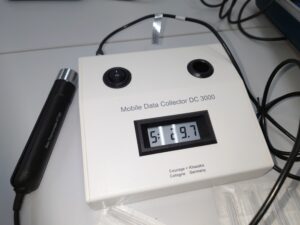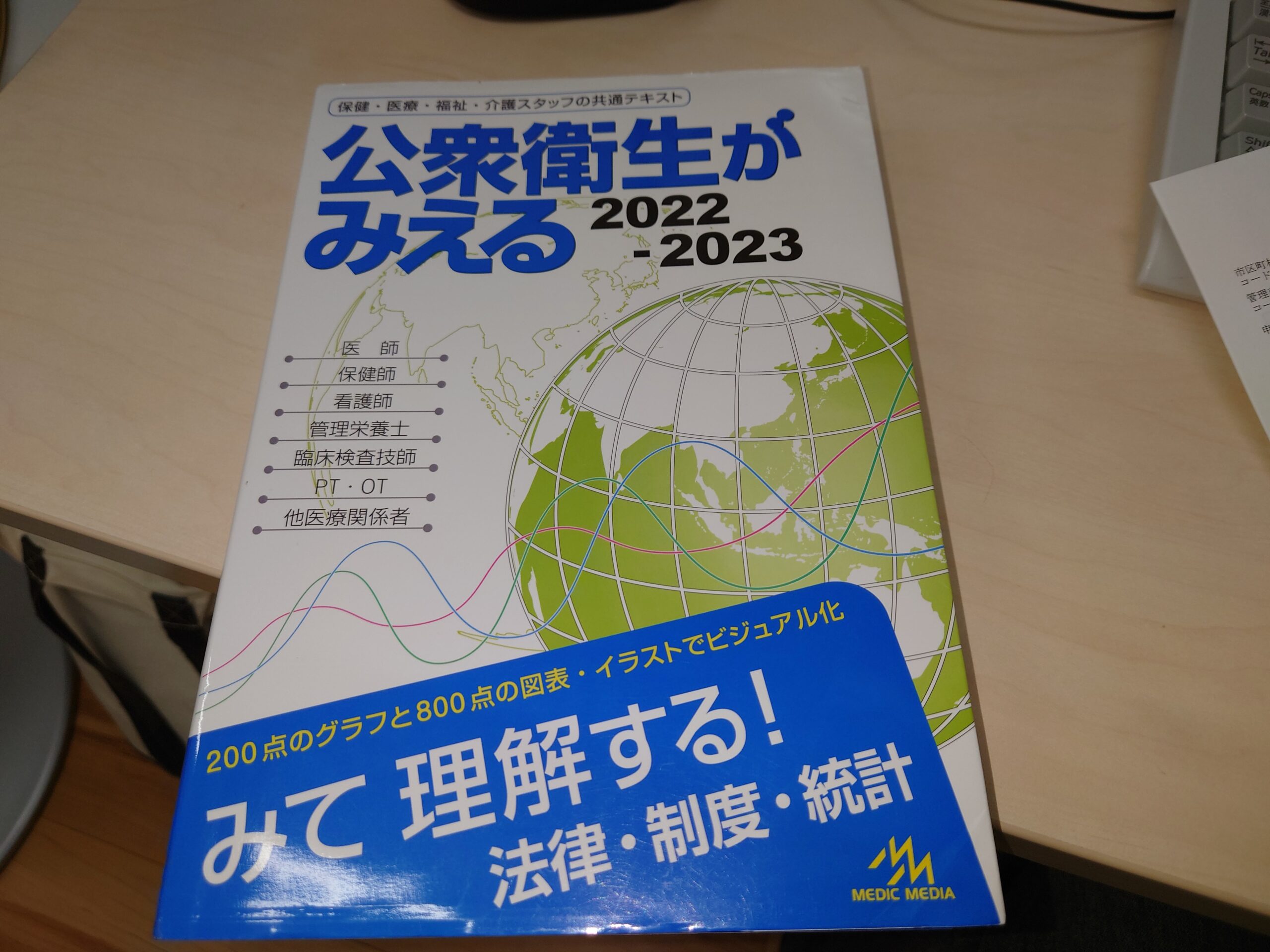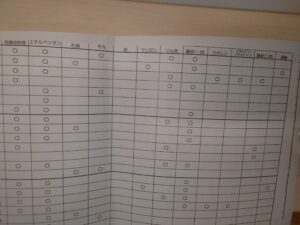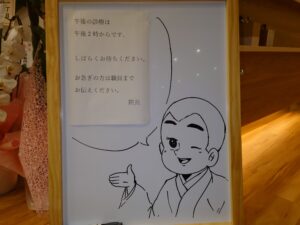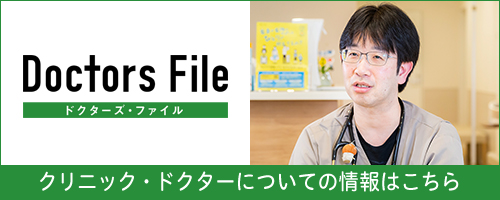鳥取大学勤務時代に第一内科(病態情報内科学講座)の循環器内科のホームページ作成の係を担当していたことがあります。その当時はまだ科としてのホームページがない時代でしたので、とりあえず他の大学がどんなホームページを作っているのか、日本の全ての大学の循環器内科のホームページを閲覧してみました。その際、今は教授を退官されておりますが、山口大学器官病態内科学の松崎益徳前教授が医学生、新人医師に向けて書かれた医師の心構えを説いた挨拶文(医局への勧誘を兼ねた内容だったと思います)を読み、当時私は非常に感銘を受けたことを覚えています。その部分をプリントスクリーンをして、大事にファイルに保管していたのですが、境港の済生会に転勤した際にどこに保管したか分からなくなり、今となっては非常に後悔しております。その内容で特に印象に残っている言葉は、目の前の患者さんは『しゃべるプロ』でも『聞くプロ』でも何でもない、ということです。私にとっては非常に大事にしている言葉で今回取り上げさせていただきましたが、要旨が異なっていますと松崎先生に大変失礼になりますので、松崎先生へのオマージュとして最近私の思っていることもつけ加えて私見として述べさせて頂きます。
患者さんから『下痢で受診したい』とのことで連絡あり、診察室に入って話しをよく聞いてみると、実は下痢はそんなに大したことはなくて、昨日からの喉の痛みと発熱で実は新型コロナウィルスに感染したのが心配したので来院しました…あくまでも一例ですが、こういうことは決して珍しくありません。『主訴』、患者さんの症状のうち最も主要なものですが、これが話しの中ではっきりしない場合もありますし、昨日からの症状の話しをしているところにその症状と関係ない3ヶ月くらい前の話しに移ったりすることもあります。患者さんは自分の考えている通りにうまく決して話してくれませんし、聞くごとに話す内容が変わることもよくあります。患者さんの訴えや病状の経過を本当にきっちりまとめるのは意外と大変なことです。ただこれは『こんな患者さんもいます』ということではなく、松崎先生の言葉を借りますと患者さんは決して『しゃべるプロ』ではないのだから、うまく話せないことを前提でしっかり患者さんの訴えに耳を傾けなさい、ということなのです。
外来では減塩であったり、心不全患者さんの体重測定などのセルフモニタリングなど毎回重要性を説明することがあります。患者さんからは『また同じこと言っている』『前回も聞いたよ』と心の中で思っておられる方もおられるでしょう。無論小生の『ど忘れ』の場合もありますが、多くはあえて繰り返していることが多いです。勤務医時代に今後の方針(多くは退院先など方向性に関しての話し)について家族を集めてお話しすることがよくありました。約30分程度、紙やタブレットを用いてソーシャル・ワーカーの方や看護師さんも交えて説明し、御返事は来院していない他の家族とも相談して、後日返事を頂くことがあります。しかし再度来院頂き話をしてみますと、最初の説明の段階のほぼ振り出しに戻っていることもよくある話しです。ここに関しては私の説明の拙さにも原因あると思います。ただこれはどんなにうまく説明したとしても一度の話しで全部理解して頂いているとは私は思っていません。失礼な表現かもしれませんが中学・高校時代でも自動車学校でも、先生の授業を聞くだけで授業内容をテストして、クラス全員がテストで満点とれるのかというと、そんなことはまずないと思います。一度話しをして、その内容の半分くらい理解してくれたらよい、そんな気持ちで説明をしております。逆を言えば、相手に十分理解頂くには複数回説明を重ねる必要も時として出てくると考えています。
患者さんとの問診や説明がうまく行かない時に、正直に申しますとイライラするような気持ちが出てくることがあります。その時にはいつも、患者さんは『しゃべるプロ』でも『聞くプロ』でも何でもない、あの言葉を思い出してます。それが実行出来ているかは自己評価としてはまだまだですが、いつかは自分が『説明のプロ』、『聞き出すプロ』になれるように今日も日常診療頑張りたいと思います。